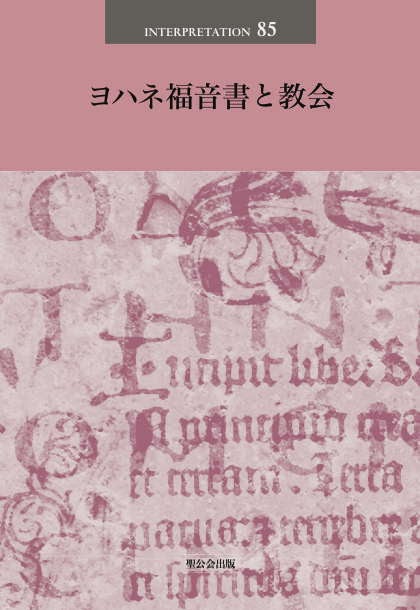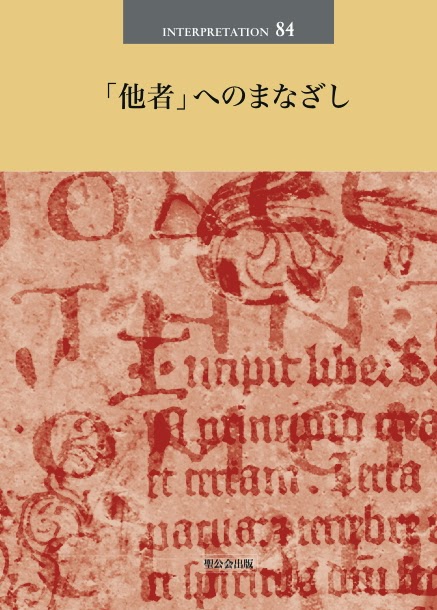ヤハウェが統治しているという主張は人間の責任を軽減させることにはならない。
むしろ、ヤハウェがすべての民―とりわけ神の民―に自分たちの行動の責任を問うているとエレミヤは強調する。
「『お前たちはお前たちの悪の道から、今立ち帰り、お前たちの道とお前たちの行いを改めよ』。
しかし、彼らは言う。『そんなことは無駄だ。われわれはわれわれの計画に従う……』」(一八11―12)。
行為の主体性こそは憂慮すべき点があるとしても、エレミヤ書における希望の本質的要素である。
ユダの苦境は大方において自分たちの行為の結果であるという信念をエレミヤはもち続けている。
トーラーの価値の破綻、とりわけ真実、正義、共感する心の崩壊が混沌と破壊を引き起こすというのだ。
この倫理的見解がある意味、犠牲者たちを非難してしまう、ということは否めない。
ユダの民の肩に責任を負わせることは、エルサレム陥落の第一級戦犯を免責するということである(とはいえエレ五〇―五一章参照)。
この因果論的議論に問題があることは認めざるを得ないが、部分的には生存者が説明のつかない苦難を理解する方策のひとつとしての役割を果たしている。
自分ではどうすることもできない地政学上の力、自然の力の犠牲になってしまった人々にとって、主体性の再確立は、たとえ他者の犠牲を通してであれ、非難を受けることを通してであれ、希望と回復の核となる要素なのである。
それは危険な力を「無力」にし、「無秩序」を一掃する。
特に、共同体の危機は理由がないわけでも無差別なものでもなく、秩序の上でも道徳の上でも一貫した意味をもつ世界がもたらす帰結なのだということを例証する役割を果たしている。
そして、エレミヤ伝承は象徴、知性、感情の混沌を抑制し、それを意味の一貫した脈絡の中に位置づけるために、申命記的理解や契約理解を含む様々な比喩を集めている(例えば、一一1―17参照)。
ルイス・J・スタルマン
危機における希望の使者エレミヤ
(インタープリテイション82号「エレミヤの肖像」)
エレミヤの肖像
第82号 2013年9月
定価2000円+税